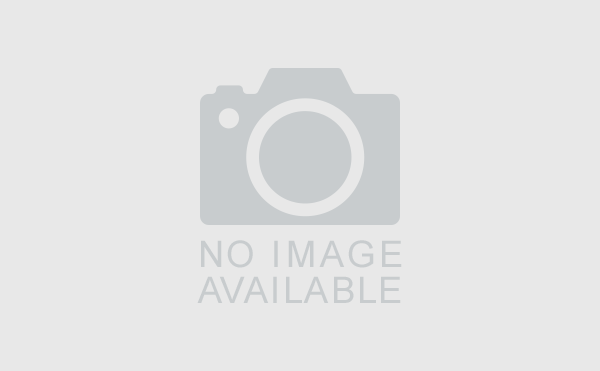インタビュー「謡曲・仕舞とは?」河西暁子さん(観世流シテ方準職分)

この夏、三鷹市能楽会では「謡曲・仕舞体験教室」(全3回)を開催。市民の皆さんが初めて謡曲や仕舞のお稽古を体験し、能の魅力に触れていただく機会となりました。今回、市民文化祭「謡曲・仕舞大会」の舞台に、参加された方の中から9名の皆さんが出演します。講師の河西暁子さん(観世流シテ方準職分)にお話を伺いました
能楽とは?

能楽とは古代からあったさまざまな芸能の影響をうけて、室町時代(14世紀)に、将軍足利義満の庇護のもと、観阿弥・世阿弥の親子が芸術にまで高めた仮面歌舞劇です。
能に用いる面(おもてと呼びます)自体も芸術品です。
謡曲・謡・仕舞とは?
この仮面舞台劇である能楽(お能)の声楽部分を謡(うたい)、舞(まい)の部分を仕舞(しまい)といいます。
『観世流初心謡本』のなかに、「謡曲とは何か、一言で言えば能楽(能とも言う)の歌謡である」とあります。
近世に入り豊臣秀吉や徳川家康など身分の高いものに愛好された能も、やがてそれを簡略化し、その一部を面も装束もつけずに演じる舞囃子(まいばやし)、さらに囃子(笛、鼓、太鼓)を抜いて、いっそう始めやすく親しみやすくした「謡と仕舞」が庶民のあいだに広まり、いまではだれもが楽しめる芸能に変わっています。
ぜひこのことを知っていただきたいと思います。
ぜんぜん敷居は高くない

体験教室の皆さん、始めは緊張気味だったのが、あっという間に笑顔になりました。
やはり伝統芸能、日本人に合っている。思い切って声を出すと、心がはればれするということでしょう 私からは「なにしろ腹式呼吸が基本なので、健康にもいいんですよ」ともお伝えしています。
3回のレッスンで舞台に

今回の舞台は、おめでたい曲「鶴亀」を大勢のひとたちが和服でうたいあげます。3回の稽古を終えたばかりの体験教室の皆さんも参加します。壮観ですよ。どうぞ気軽にご覧ください。
謡曲・仕舞大会 10月26日(日) 会場:芸術文化センター星のホール

海外からも高い評価を得ている
能の魅力にふれてみませんか?
主管団体:三鷹市能楽会
主催:三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会
令和7年度 三鷹市市民文化祭日程
「お稽古してみませんか?」シニアクラス(謡)初心者・経験者対象
毎月第1・2・3金曜日 13:30~15:00
会場:高齢者福祉センター(元気創造プラザ3階)
参加費:月3,000円
講師:河西暁子(観世流シテ方準職分)*月1回の指導あり
都立三鷹高校卒、東京藝術大学音楽学部邦楽科能楽専攻卒業、
観世流宗家派、観世会員、能楽協会会員
申込・問合せ先:三鷹市能楽会 電話090-9399-1654